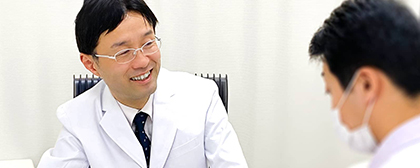梅毒、クラミジア、マイコプラズマ・ウレアプラズマ属細菌における
抗菌薬治療効果の観察研究
当クリニックでは性感染症診療における診断や治療を向上させるべく研究に取り組んでいます。性感染診療において未解明なことや科学的根拠が確かでないことが数多く見られるため、皆様の診療に真摯に取り組んできた記録となる診療録の情報を活用し、今後のより良い診療につなげていくことを目的としています。研究にあたって皆様にご負担いただくことは一切ありません。この研究は東京大学医学部附属病院とプライベートケアクリニック東京による共同研究です。
この研究の対象者に該当する可能性がある方で、診療情報等を研究目的に利用または提出されることを希望されない場合は2025年9月30日までに末尾に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
研究課題
梅毒、クラミジア、マイコプラズマ・ウレアプラズマ属細菌における抗菌薬治療効果の観察研究(審査番号 2025105NI)
研究機関名及び自機関の研究責任者氏名
この研究が行われる研究機関と研究責任者は次に示すとおりです。
- 研究機関
- プライベートケアクリニック東京
- 研究責任者
- 小堀 善友(東京院 院長)
- 機関の長
- 小堀 善友(東京院 院長)
- 担当業務
- データ取得および提供
共同研究機関
- 主任研究機関
- 東京大学医学部附属病院 感染症内科
- 研究責任者
- 堤 武也(感染症内科 教授)
- 担当業務
- 研究計画立案・データ解析
この研究に利用する情報は、研究機関(東京大学医学部附属病院およびプライベートケアクリニック東京)の範囲のみで利用されます。
研究期間
承認日~2029年12月31日
対象となる方
- 2017年4月1日 ~ 2024年12月31日の間にプライベートケアクリニック東京 新宿院あるいは東京院で、以下の診療を受けられた方
- 早期梅毒の診断を受けて、ミノサイクリンまたはベンザチンペニシリンGによる治療を受けた方
- クラミジア感染症の診断を受けて、抗菌薬で治療を受けた方
- マイコプラズマまたはウレアプラズマ感染症の診断を受けて、抗菌薬で治療を受けた方
研究目的・意義
性感染症はリスクがあれば誰でもかかってしまう可能性があること、時に自覚症状が乏しく適切に受診や検査を受けることが難しいこと、また適切な診断・治療を受けられないことで感染が広がってしまうことや、個人に重大な合併症を起こす可能性があるため、現代においても脅威となる感染症です。
性感染症の診療にあたって国内外のガイドラインが整備されつつあるものの、ガイドライン同士の見解が一致しないことや、ガイドラインに詳しく記載されていないテーマもみられます。そこで本研究では、梅毒、クラミジア、マイコプラズマ属細菌あるいはウレアプラズマ属細菌などの性感染症を対象に、治療方法による治療効果の違いを検証し、最適な治療方法について検討することを目的としています。具体的には以下の検討を予定しています。
早期梅毒における国際的な標準治療としてベンザチンペニシリンG筋注240万単位単回投与が推奨されており、本邦のガイドラインでは第二選択薬をミノサイクリン100mg 1日2回投与28日間投与としています。しかし、ミノサイクリンによる早期梅毒に対する最適な治療期間や治療成績については十分な研究が行われていないため、本研究では早期梅毒に対してミノサイクリンを2週間投与された群と、ベンザチンペニシリンG筋注単回投与で治療された群を比較し、その治療成績について検討する予定です。
クラミジア感染症に関しては世界的にはドキシサイクリンによる治療を第一選択として第二選択薬をアジスロマイシンと位置づけており、その他状況によりレボフロキサシンによる治療が考慮される状況にあります。本邦では上記に加え、ミノサイクリン、シタフロキサシンなども治療選択肢に挙げられているものの、薬剤同士を比較した研究が乏しいのが現状です。そこで本研究ではクラミジア感染症に対して用いた抗菌薬の治療成績を比較し、最適な治療について検討する予定です。
ウレアプラズマ属やマイコプラズマ・ホミニスを保菌している状態で治療の必要性があると判断した場合に、マクロライド系、テトラサイクリン系、キノロン系、リンコサミド系抗菌薬が代表的な選択肢となります。しかしこれらのどの薬剤が特に有効であるかは十分な研究が行われておらず、最適な治療について知見の蓄積が必要です。本研究においてマイコプラズマまたはウレアプラズマ感染症に対して用いた抗菌薬の治療成績を比較し、最適な治療について検討する予定です。
研究の方法
- 2017年4月1日~2024年12月31日までの期間において、プライベートケアクリニック東京を受診され、早期梅毒に対してベンザチンペニシリンGまたはミノサイクリンで治療を受けた方、クラミジア感染症に対して抗菌薬治療を受けた方、マイコプラズマまたはウレアプラズマ感染症に対して抗菌薬治療を受けた方10,000人を対象として、過去の診療情報を収集します
- カルテに記録されている年齢、性別、背景疾患、服薬歴、アレルギー歴、現病歴、性行為を含む社会歴、身体所見、検査所見、臨床診断、治療内容を収集します。特に研究対象者の皆さんに新たにご負担いただくことはありません。
- プライベートケアクリニック東京で収集した情報を東京大学に提供いたします。事前にプライベートケアクリニック東京においてデータから氏名・住所・患者IDといった個人情報を取り除き、ファイルにパスワードロックをかけ、クラウドサービスを用いて研究チーム内のみで共有します。パスワードは電子メールを用いて共有します。
利用又は提供を開始する予定日:2025年10月1日
なお、研究計画書や研究の方法に関する資料を入手・閲覧して、研究内容を詳しくお知りになりたい場合は、末尾の連絡先にお問い合わせください。他の研究対象者の個人情報等の保護や研究の独創性確保に支障がない範囲でご提供させていただきます。
個人情報の保護
この研究に関わって収集される資料・情報等は、外部に漏えいすることのないよう、慎重に取り扱う必要があります。
取得した資料・情報等は、氏名・住所・生年月日・患者IDなどの個人情報を削り、代わりに新しく研究用の符号をつけ、どなたのものか分からないようにします。
どなたのものか分からないように加工した資料・情報等は、東京大学に送られ解析・保存されます。研究担当者のみ使用できるパスワードロックをかけたパソコンを、鍵のかかる室内で厳重に保管します。ただし、必要な場合には、プライベートケアクリニック東京においてこの符号を元の氏名等に戻す操作を行うこともできます。
この研究のためにご自分(あるいはご家族)の情報・データ等を使用してほしくない場合は主治医にお伝えいただくか、下記の問い合わせ先に2025年9月30日までにご連絡ください。研究に参加いただけない場合でも、将来にわたって不利益が生じることはありません。
ご連絡をいただかなかった場合、ご了承いただいたものとさせていただきます。
研究の成果は、あなたの氏名等の個人情報が明らかにならないようにした上で、学会発表や学術雑誌で公表します。
取得した情報・データ等は厳重な管理のもと、研究終了後5年間保存されます。保管期間終了後には、紙媒体の資料はシュレッダーにかけ、電子データはファイル削除ソフトにかけることで廃棄します。なお研究データを統計データとしてまとめたものについてはお問い合わせがあれば開示いたしますので下記までご連絡ください。
尚、提供いただいた情報の管理の責任者は下記の通りです。
- 情報の管理責任者
- 所属:プライベートケアクリニック東京 東京院
氏名:小堀 善友
本研究の結果として知的財産権等が生じる可能性がありますが、その権利は国、研究機関、共同研究機関および研究従事者等に属し、研究対象者はこの特許権等を持ちません。また、その知的財産権等に基づき経済的利益が生じる可能性がありますが、これについての権利も持ちません。
この研究は、東京大学医学部倫理委員会の承認を受け、プライベートケアクリニック東京 東京院長 小堀善友の許可を受けて実施するものです。
この研究に関する費用は、東京大学医学部附属病院感染症内科、東京大学 保健・健康推進本部の運営費から支出されています。
本研究に関して、開示すべき利益相反関係はありません。
尚、あなたへの謝金はございません。
この研究について、わからないことや聞きたいこと、何か心配なことがありましたら、お気軽に下記の連絡先までお問い合わせください。
2025年6月
【連絡・お問い合わせ先】
- 研究責任者: 小堀 善友
- 連絡担当者: 稲田 誠
-
〒103-0027 東京都中央区日本橋
2-2-2マルヒロ日本橋ビル4F・1F - プライベートケアクリニック東京
- Tel:03-5255-6611
※研究全体の連絡先
- 研究責任者:堤 武也
- 連絡担当者:稲田 誠
- 〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
- 東京大学医学部附属病院 感染症内科
- 電話:03-3815-5411(内線 37280 )
- FAX:03-5800-9102
- e-mail:makotoinada@g.ecc.u-tokyo.ac.jp